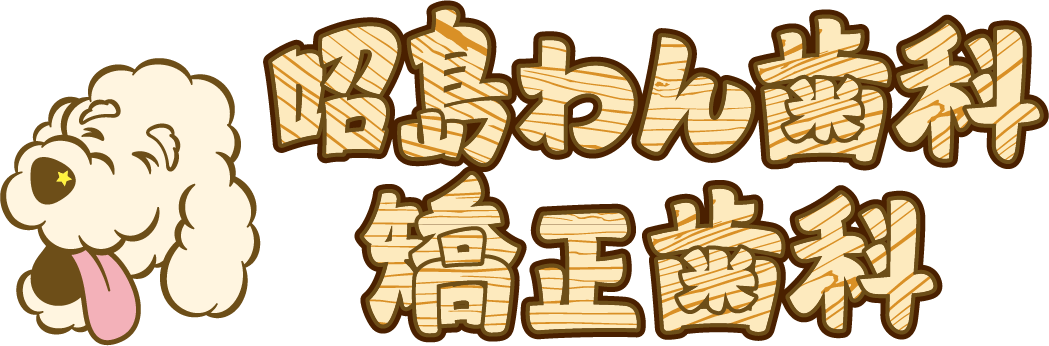2025年10月23日
歯ぎしり・食いしばりが体に及ぼす影響とは?
寝ている間や集中している時、無意識のうちに歯を強く噛みしめていませんか?
実はこの「歯ぎしり」や「食いしばり」は、歯や顎だけでなく、全身にさまざまな悪影響を及ぼすことがあります。
■ 歯への影響
強い力で歯同士をこすり合わせることで、
-
歯がすり減る
-
ヒビが入る
-
詰め物や被せ物が外れる・欠ける
といったトラブルが起こります。
ひどい場合には、歯の神経に炎症が起きたり、最終的に歯を失ってしまうこともあります。
■ 顎関節への影響
歯ぎしりや食いしばりは、顎関節症の原因にもなります。
顎の関節や筋肉に過剰な負担がかかることで、
-
顎が痛む
-
口を開けにくい
-
カクカク音がする
といった症状が現れることがあります。
これらの症状を放置すると、慢性的な痛みや頭痛につながる場合もあります。
■ 頭・首・肩への影響
歯ぎしりや食いしばりを続けていると、咬筋(こうきん)や首・肩の筋肉が常に緊張した状態になります。
その結果、
-
頭痛
-
肩こり
-
首のだるさ
など、体の不調として現れることがあります。
中には、原因がわからず整形外科を受診しても改善せず、歯科で相談して初めて原因がわかるケースもあります。
■ 自律神経や睡眠への影響
睡眠中の歯ぎしりは、無意識のうちに体を緊張状態に保つため、深い眠りの妨げになることも。
寝ても疲れが取れにくい、朝起きると顎がこわばっているという方は、歯ぎしりが原因の可能性があります。
■ 歯ぎしり・食いしばりの対策
原因はストレスや噛み合わせ、生活習慣などさまざまですが、
歯科では次のような方法で対処できます。
-
**ナイトガード(マウスピース)**の装着
→ 就寝中の歯ぎしりから歯や顎を守ります。 -
噛み合わせの調整
→ 特定の歯に過度な負担がかかっている場合に有効です。 -
ストレスケアや生活習慣の見直し
→ 無意識の食いしばりを減らすためのリラックス法も大切です。
■ まとめ
歯ぎしりや食いしばりは、「クセだから仕方ない」と放置してしまいがちですが、
実は全身の不調の原因になることもある深刻な症状です。
もし朝起きたときに顎の疲れを感じたり、歯がすり減っているように思う方は、
ぜひご相談ください。
早めの対策が、歯や体を守る第一歩になります。